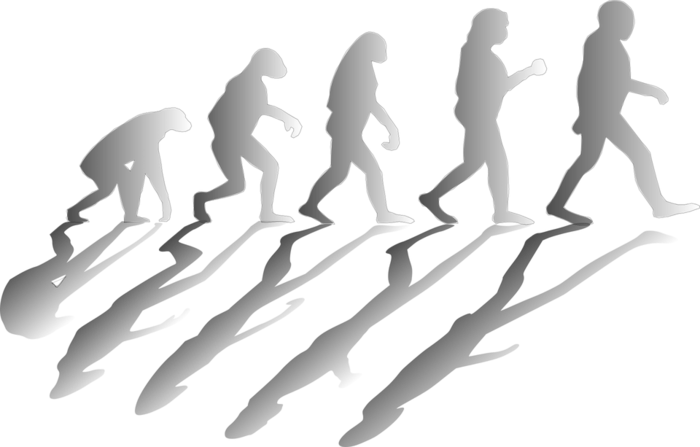[allpage_toc]
珍渦虫の正体と特徴
北ヨーロッパの海の底100メートルの泥の中に、顔がない謎の生き物が蠢いています。それは、珍渦虫と呼ばれる生物です。この生物を謎と知らしめてた理由として、生物に当然としてあるはずの脳みそや、繁殖のための生殖器を持っていないからです。それが、珍渦虫が謎の生物と言われる所以です。その珍渦虫の所以が世界中の生物学者の好奇心を掴んでいました。
珍渦虫がいる場所
珍渦虫が初めて発見されたのは1878年で、珍渦虫が報告されたのは1949年です。1949年に珍渦虫が報告された時に発見された場所はスウェーデン沖と言われ、この場所は唯一、珍渦虫が定期的に見つかる場所がスウェーデンの沖合の水深100メートルの、深くて寒くて、暗い場所です。
水深100メートルの海底をトロール漁、底引き網漁をすれば珍渦虫がすぐに見つかるとは言い難く、海底をさらって泥を濾してその残りから手作業で探し出します。一回の漁でも見つかる珍渦虫は数匹から数十匹ほどです。珍渦虫はスウェーデン沖以外にも、スカンディナビア半島の地中海である、バルト海にも生息していると言われています。
水深100メートルの海底をトロール漁、底引き網漁をすれば珍渦虫がすぐに見つかるとは言い難く、海底をさらって泥を濾してその残りから手作業で探し出します。一回の漁でも見つかる珍渦虫は数匹から数十匹ほどです。珍渦虫はスウェーデン沖以外にも、スカンディナビア半島の地中海である、バルト海にも生息していると言われています。
珍渦虫の大きさ
珍渦虫の大きさは幅が5㎜ほどで縦の長さが大体1㎝~3㎝で、4㎝はあるという情報もあります。取り合えず、目視はできるが小さいことには変わりないです。珍渦虫は長細い形をしていますが、厚みはなぺったんこの扁平で、左右対称の形をしています。
珍渦虫の形態
この小さな体の珍渦虫は生物としてかなりの変わり者です。なぜなら、生物として「ある」ものよりも「ない」ものの方が多いです。それは、脳がないです。生殖器がないです。中枢神経がないです。目がないです。骨がないです。肛門がないです。
珍渦虫は先に書いたもの以上に、我々が生物が持っているものがないです。その一方で、口とそれに続く腸があることは確認されています。珍渦虫は体の構造はかなりシンプルにできています。我々、人間から見ると、必要最低限の機能さえ珍渦虫には備わっていません。
珍渦虫は先に書いたもの以上に、我々が生物が持っているものがないです。その一方で、口とそれに続く腸があることは確認されています。珍渦虫は体の構造はかなりシンプルにできています。我々、人間から見ると、必要最低限の機能さえ珍渦虫には備わっていません。
珍渦虫には口はある
口があるということは珍渦虫は摂食活動を行うということです。しかし、肛門がありません。排泄物を出さないということでしょうか。食べたものは、全て消化してしまうのでしょうか。また、生殖器がないため繁殖行為ができません。
それにも関わらず、珍渦虫は繁殖しているという報告があります。この繁殖の仕方については明らかになったところもあり、後に詳しく説明をします。
それにも関わらず、珍渦虫は繁殖しているという報告があります。この繁殖の仕方については明らかになったところもあり、後に詳しく説明をします。
珍渦虫とは、珍しい「渦虫」
珍渦虫が発見されたとき、この謎過ぎる生物をどこに分類するか学者たちは悩みました。古い論文によりますと、二枚貝の近縁の軟体動物ではないかと考えられていましたが、あまりにも体の構造が違うため、疑問がありました。一応、珍渦虫のDNAを調べ分類していくのですが、DNAサンプルの中に珍渦虫が食べた軟体動物の幼生が混入していたため二枚貝の仲間と思われたと言われています。
しかし、珍渦虫という名前からして、珍しい渦虫と考えられていたことがわかります。珍渦虫が発見された当初は、珍しい渦虫の仲間だと思われていました。よって、珍渦虫という名前が付けられました。
しかし、珍渦虫という名前からして、珍しい渦虫と考えられていたことがわかります。珍渦虫が発見された当初は、珍しい渦虫の仲間だと思われていました。よって、珍渦虫という名前が付けられました。
渦虫とは?
渦虫とは扁形動物門ウズムシ綱ウズムシ目ウズムシ亜目に属する動物の総称のことです。小難しい言い方ですが、生物上、最も再生能力にたけた生き物・プラナリアのことです。珍渦虫は一見すると、プラナリアのように見える左右相称動物だったため、プラナリアの仲間なのではないかと思われていました。
しかし、珍渦虫は渦虫と全く異なる生き物でした。しかし、珍渦虫には、扁形動物にあるはずの原始的な中枢神経がありません。先にも書きましたが、珍渦虫にはないもの尽くしの生き物です。感覚器官、運動器官、生殖器官。しかし、消化器官は腸だけはあります。
ウズムシ目とは三岐腸目ともいわれ、三岐腸とは腸が3つに分かれていることを意味しています。よって、渦虫の腸は3つに分かれています。珍渦虫は腸はあることは確認されていますが、渦虫と同じ分類に入れなかったところを見ると、珍渦虫の腸は3つには分かれてはいないのでしょう。
しかし、珍渦虫は渦虫と全く異なる生き物でした。しかし、珍渦虫には、扁形動物にあるはずの原始的な中枢神経がありません。先にも書きましたが、珍渦虫にはないもの尽くしの生き物です。感覚器官、運動器官、生殖器官。しかし、消化器官は腸だけはあります。
ウズムシ目とは三岐腸目ともいわれ、三岐腸とは腸が3つに分かれていることを意味しています。よって、渦虫の腸は3つに分かれています。珍渦虫は腸はあることは確認されていますが、渦虫と同じ分類に入れなかったところを見ると、珍渦虫の腸は3つには分かれてはいないのでしょう。
珍渦虫の正体
結局のところ、体の構造があまりにも簡素で、奇妙な珍渦虫は分類するのが困難でした。よって、動物門不明状態が続きました。よって、先にも書いたような二枚貝の近縁種だという論文や説が出てきては否定され、消えていきました。
中には、珍渦虫の個性的な体の構造。つまり簡素な構造の理由として、一度高度に発達したけれど、何らかの理由で二次的に退化したという説が出てきましたが、DNAの解析をしてみるとそうではないことがわかりました。
[no_toc]
中には、珍渦虫の個性的な体の構造。つまり簡素な構造の理由として、一度高度に発達したけれど、何らかの理由で二次的に退化したという説が出てきましたが、DNAの解析をしてみるとそうではないことがわかりました。
珍渦虫は無腸動物の近縁
この謎の生物・珍渦虫をどこに分類しようかと、いろいろ研究が進められ、DNAを調べてみると珍渦虫は独自グループに分類すべきだと言う意見が出てきました。もう、珍渦虫動物門で定義しようではないかと言います。しかし、さらに有力な分類分けができるという説が出てきました。
珍渦虫を無腸動物門にカテゴライズできる。と言いう説が出てきました。珍渦虫は無腸動物と近縁だと主張が出ました。しかし、この無腸動物も分類上どこに属していいのか、位置が定かではない、不明確な生物です。珍渦虫も無腸動物も、分類上の位置が不明確というお仲間というのは納得できるでしょう。
珍渦虫を無腸動物門にカテゴライズできる。と言いう説が出てきました。珍渦虫は無腸動物と近縁だと主張が出ました。しかし、この無腸動物も分類上どこに属していいのか、位置が定かではない、不明確な生物です。珍渦虫も無腸動物も、分類上の位置が不明確というお仲間というのは納得できるでしょう。
珍渦虫と無腸動物の関係
珍渦虫と無腸動物は同じ仲間という考えは以前からあり、一時期は無腸動物は渦虫と同じ分類、扁形門ではないかと考えられていました。これは外見上が似ていたためですが、外見が似ていても違うと指摘され、独自グループの無腸動物門という独立した分類になりました。
2016年の研究結果によると、珍渦虫と無腸動物と姉妹関係にあると示されたとあり、珍渦虫は珍無腸動物門という動物門の構成を提唱しました。
2016年の研究結果によると、珍渦虫と無腸動物と姉妹関係にあると示されたとあり、珍渦虫は珍無腸動物門という動物門の構成を提唱しました。
ネイチャーに掲載された珍渦虫の概要と位置づけ
分類上の位置がやっと明確になった珍渦虫ですが、この生物は動物の進化の初期段階に位置する生物だと言う説が出ています。要するに、目がないささみをぺったんこにしたような容姿をしている生物が、我々人間の始まりだと言います。本当に単純な生命から我々人間が始まったことになります。
珍渦虫は何にでもなれる
この動物の進化の初期段階説は、米国とオーストラリアの研究チームがネイチャー紙に発表された説です。珍渦虫が生物の進化の初期段階にあることには違いないのですが、補足すると、進化の枝分かれ部分に位置する生物だと言われてます。
進化の途中にいる生物であり、つまり、この珍渦虫は何にでもなれる生物となります。
進化の途中にいる生物であり、つまり、この珍渦虫は何にでもなれる生物となります。
単純な生物
先述しましたが、珍渦虫は一度進化して退化したという説がありました。今回のネイチャーに発表された論文によりますと、珍渦虫は元から単純な生き物だという結論がでました。
しかし、元からシンプルな作りをしている珍渦虫ですが、生物分類上、ヒトが含まれる脊索動物門に比較的近い位置にいると言われています。よって、寒い海底にいる珍渦虫の中にはヒトに進化するものもいるのでしょう。
しかし、元からシンプルな作りをしている珍渦虫ですが、生物分類上、ヒトが含まれる脊索動物門に比較的近い位置にいると言われています。よって、寒い海底にいる珍渦虫の中にはヒトに進化するものもいるのでしょう。
単純な生物の不思議な体
この珍渦虫は口があるが、肛門がない。口があるから何かしらものを食べていることはわかっています。ただ、珍渦虫が一体何を食べて、生命活動を維持しているのかはわかっていません。
二枚貝の仲間説の時に、珍渦虫のDNAに二枚貝の情報が混ざったことがありましたが、これは珍渦虫が食べたことによるものという可能性があるとも言われています。よって、二枚貝系の生物を食べている=肉食か雑食の生物だとはわかります。
口に続く腸もあるのですが、肛門がないので、排泄はどのように行っているのか不思議です。珍渦虫は口が肛門の役目を担っており、口と肛門を兼用するという生物は結構います。クラゲやサンゴやイソギンチャクが、珍渦虫同じような食べ方、排泄をします。このような生物たちをひとまとめにして、腔腸動物と言われています。
二枚貝の仲間説の時に、珍渦虫のDNAに二枚貝の情報が混ざったことがありましたが、これは珍渦虫が食べたことによるものという可能性があるとも言われています。よって、二枚貝系の生物を食べている=肉食か雑食の生物だとはわかります。
口に続く腸もあるのですが、肛門がないので、排泄はどのように行っているのか不思議です。珍渦虫は口が肛門の役目を担っており、口と肛門を兼用するという生物は結構います。クラゲやサンゴやイソギンチャクが、珍渦虫同じような食べ方、排泄をします。このような生物たちをひとまとめにして、腔腸動物と言われています。
珍渦虫の繁殖の仕方
生殖器も持たない珍渦虫が一体どのように繁殖しているのか気になります。はっきり言って、まだよくわかっていません。元々卵で繁殖することはわかっていたのですが、その後どうやって成長するかははっきりしていませんでした。
そして、今でもはっきりとした繁殖方法がわかっていません。生殖器がないのに繁殖と言えば細胞分裂を行うのですが、卵を産むことはわかっています。しかし、生殖器もないのに卵を産みます。珍渦虫の繁殖方法は細胞分裂で増え、生殖器がないのに卵を産む(卵が産める?)という、奇妙な繁殖を行います。結局のところ、発生過程は謎のままです。
珍渦虫の奇妙な繁殖方法を報告したのは、筑波大学を始めとした国際研究チームで、筑波大学では繁殖方法だけではなく、世界初の珍渦虫の幼生の観察の成功しました。
そして、今でもはっきりとした繁殖方法がわかっていません。生殖器がないのに繁殖と言えば細胞分裂を行うのですが、卵を産むことはわかっています。しかし、生殖器もないのに卵を産みます。珍渦虫の繁殖方法は細胞分裂で増え、生殖器がないのに卵を産む(卵が産める?)という、奇妙な繁殖を行います。結局のところ、発生過程は謎のままです。
珍渦虫の奇妙な繁殖方法を報告したのは、筑波大学を始めとした国際研究チームで、筑波大学では繁殖方法だけではなく、世界初の珍渦虫の幼生の観察の成功しました。
珍渦虫の成長を解明した筑波大学の珍渦虫に関する研究内容
[no_toc]世界初の珍渦虫の幼生の観察に成功したのは、筑波大学の中野裕昭助教授です。中野氏は元々ウミユリという棘皮動物の研究をしていました。ヒトは脊索動物門に属しています。これと進化的に近いのが、中野氏が研究している棘皮動物門です。これに半索動物門と、ヒトが所属する脊索動物門は新口動物と言われています。
これらは、受精卵となり細胞分裂がおこる過程で、口よりも肛門が先にできる生物のことです。2003年に珍渦虫は新口動物だという論文が発表されました。先述しましたが、珍渦虫は肛門がありません。これに、興味を抱いたのが、筑波大学の中野裕昭助教授です。
これらは、受精卵となり細胞分裂がおこる過程で、口よりも肛門が先にできる生物のことです。2003年に珍渦虫は新口動物だという論文が発表されました。先述しましたが、珍渦虫は肛門がありません。これに、興味を抱いたのが、筑波大学の中野裕昭助教授です。
珍渦虫の幼生の観察
珍渦虫の繁殖期の冬(繁殖シーズンは判明しているようです)に、スウェーデン沖の海底で見つけた珍渦虫を実験室に持ち込んで、飼育・観察します。そして、珍渦虫の幼生の観察に成功しました。なんと、珍渦虫の卵の確認もできました。
しかし、どのような過程で受精卵が発生したのは不明とのこと。しかも、せっかく見つかった幼生も8日後には死亡が確認されました。
しかし、どのような過程で受精卵が発生したのは不明とのこと。しかも、せっかく見つかった幼生も8日後には死亡が確認されました。
珍渦虫の幼生についてわかったこと
現在、中野助教授は下田臨海実験センターという、筑波大学の施設でスウェーデン沖から持ち帰った珍渦虫のデータ解析と、従来行っていたウミユリと平板動物門の研究を行っています。スウェーデン沖で採取した生殖可能な珍渦虫をこの実験センターに持ち帰り、飼育したところ9個(9匹?)の幼生が得られました。
珍渦虫の幼生の確認は世界で初めてのことで、その幼生はなんとわずか5日ほどで成体とほぼ同じ構造になることを確認しました。今まで、珍渦虫の幼生を確認できなかったため、成体過程を観察できたことは、今後の研究の大きな飛躍になります。
そして、気になる珍渦虫の幼生についてですが、珍渦虫は幼生の時の方が「納得する」な体をしています。その納得する理由として、消化管がない極めて単純な体をしているとのことです。
珍渦虫の幼生の確認は世界で初めてのことで、その幼生はなんとわずか5日ほどで成体とほぼ同じ構造になることを確認しました。今まで、珍渦虫の幼生を確認できなかったため、成体過程を観察できたことは、今後の研究の大きな飛躍になります。
そして、気になる珍渦虫の幼生についてですが、珍渦虫は幼生の時の方が「納得する」な体をしています。その納得する理由として、消化管がない極めて単純な体をしているとのことです。
珍渦虫の幼生の情報はいろいろあるようです。
珍渦虫の幼生が消化管がないという単純な体をしている「つくばサイエンスニュース」からの情報で、ネットで検索してみると、中には珍渦虫の幼生は完全な消化器や肛門もあり、足や中枢神経もあるという情報がありました。
このような情報はソースが不明なものだったので、今回は「つくばサイエンスニュース」からの情報を紹介します。珍渦虫の幼生の大きさはおよそ0.23㎜で、体中に生えた繊毛を使って泳ぎます。また、幼生はかぐや姫なみの成長するのですが、成長に必要なエサは食べないことがわかりました。
珍渦虫の幼生は生命活動にも成長にも必要なエサを食べない不思議な生物です。
このような情報はソースが不明なものだったので、今回は「つくばサイエンスニュース」からの情報を紹介します。珍渦虫の幼生の大きさはおよそ0.23㎜で、体中に生えた繊毛を使って泳ぎます。また、幼生はかぐや姫なみの成長するのですが、成長に必要なエサは食べないことがわかりました。
珍渦虫の幼生は生命活動にも成長にも必要なエサを食べない不思議な生物です。
珍渦虫が紫色の靴下と呼ばれる理由
スウェーデン沖、もしくはスカンジナビア半島の内海である、バルト海辺りしかいないと思われていた珍渦虫ですが、2016年にアメリカの深海でも発見されています。発見したのはカリフォルニア大学・サインディエゴ校のスクリップス海洋研究所です。発見された珍渦虫は4種類もありました。この発見までは、1属2種類のみ知られていました。
元々12年前にも珍渦虫の新種が発見されていました。モントレー湾の海底を二枚貝をさらっていた時に発見されました。発見された珍渦虫の新種は、その外見上の特徴が脱ぎ捨てられた靴下のようで、冗談交じりに「紫色の靴下」と呼ばれることになりました。
2016年に発見された珍渦虫の新種の一つは、今までの大きさである3㎝前後より、6倍~7倍もある20㎝という大きさで、本当に靴下のような大きさです。アメリカの深海にも珍渦虫がいることわかり、日本の深海にもまだ見つかっていない珍渦虫がいる可能があります。
元々12年前にも珍渦虫の新種が発見されていました。モントレー湾の海底を二枚貝をさらっていた時に発見されました。発見された珍渦虫の新種は、その外見上の特徴が脱ぎ捨てられた靴下のようで、冗談交じりに「紫色の靴下」と呼ばれることになりました。
2016年に発見された珍渦虫の新種の一つは、今までの大きさである3㎝前後より、6倍~7倍もある20㎝という大きさで、本当に靴下のような大きさです。アメリカの深海にも珍渦虫がいることわかり、日本の深海にもまだ見つかっていない珍渦虫がいる可能があります。
チュロスとも呼ばれています
紫色の靴下と呼ばれる珍渦虫は他にもいろんな呼び方があり、靴下ワームはもちろん、研究者の中にはチュロスや、チュロス珍渦虫とも言われています。なんでも、表面のヒダがチュロス記事に似ているからという理由ということです。
一応、珍渦虫はタンパク質でできているので食べれないことはないですが、この生物自体が何を食べてできているのかも不明な生物なので、正直食べてみたいとは思う人はいないでしょう。
一応、珍渦虫はタンパク質でできているので食べれないことはないですが、この生物自体が何を食べてできているのかも不明な生物なので、正直食べてみたいとは思う人はいないでしょう。
珍渦虫のライフサイクル
単純な体を持つ珍渦虫のライフサイクルは、ひたすら繁殖をするというものに見えます。生殖器がないため、有性生殖が可能とは思えません。だから、より良い個体や子孫を残すということもできないでしょう。そして、目がないので、どうやってエサをとるのかも不明です。
そもそも脳がないので、意識がないということになります。お腹が空いたこともわからないということです。珍渦虫を見ていると、繁殖を繰り返すというのが、生物の原始的なライフスタイルなのでしょう。この珍渦虫そのものが単純な生命体として生きているので、原始的なライフスタイルなのも納得はします。
しかし、脳がないということは意識がないと言うことで、好きなこともわからず、ただ繁殖を繰り返す生命が珍渦虫です。何をもって進化をしなかったのかとても不思議です。しかし、進化をすることは生命にとって良いことなのかは全くわかりません。人間が決めつけることではないでしょう。
そもそも脳がないので、意識がないということになります。お腹が空いたこともわからないということです。珍渦虫を見ていると、繁殖を繰り返すというのが、生物の原始的なライフスタイルなのでしょう。この珍渦虫そのものが単純な生命体として生きているので、原始的なライフスタイルなのも納得はします。
しかし、脳がないということは意識がないと言うことで、好きなこともわからず、ただ繁殖を繰り返す生命が珍渦虫です。何をもって進化をしなかったのかとても不思議です。しかし、進化をすることは生命にとって良いことなのかは全くわかりません。人間が決めつけることではないでしょう。
珍渦虫は何になる?
進化を放棄したように見える珍渦虫ですが、もしかしたらこれから進化をするの可能性はあります。珍渦虫は進化の枝分かれをする初期段階にいる生命です。これから、何にでもなれるということです。暗く寒い海底でその時を待っているのでしょうか。
地球があるうちに進化をするかはわからないですが、珍渦虫の進化は人間にとって長い時間となるでしょう。
地球があるうちに進化をするかはわからないですが、珍渦虫の進化は人間にとって長い時間となるでしょう。
進化論を信じますか?
[no_toc]珍渦虫は我々人類の進化を知る上で重要な生物として注目されています。我々人類はサルが先祖だと言う進化論が当たり前となっています。しかし、サルより前の時期が人類にもあったはずです。恐竜が何らかの原因で絶滅した時代(ユカタン半島に隕石衝突が有力説)、哺乳類が必死に生き残っていたわけで、その前にも哺乳類の先祖もいたはずです。
珍渦虫は生命が何者かになる、枝分かれをする位置にいる生物と言われています。これは、人間がだった一つの受精卵から始まったと言うのと同じようにも思えます。そう考えると、進化論を受け入れることもできますが、何となく懐疑的な方もいらっしゃるでしょう。
今後、珍渦虫の研究はまだまだ時間がかかるようですが、明確になれば人類の進化についてもわかるのではないかと言われています。今後の珍渦虫の研究に期待しましょう。
珍渦虫は生命が何者かになる、枝分かれをする位置にいる生物と言われています。これは、人間がだった一つの受精卵から始まったと言うのと同じようにも思えます。そう考えると、進化論を受け入れることもできますが、何となく懐疑的な方もいらっしゃるでしょう。
今後、珍渦虫の研究はまだまだ時間がかかるようですが、明確になれば人類の進化についてもわかるのではないかと言われています。今後の珍渦虫の研究に期待しましょう。