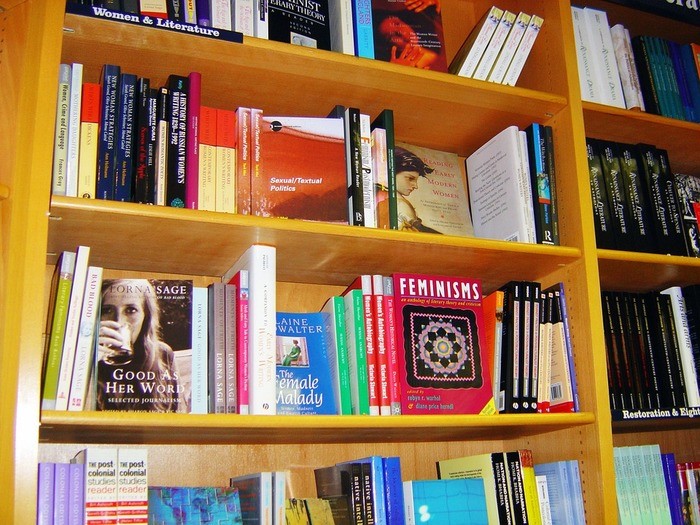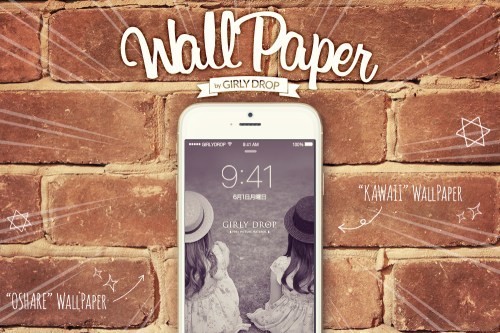カーテンの選び方|色柄別/サイズ別/機能で選ぶポイント
更新日:2025年03月05日

夜の外灯の光などが気になる方の選び方は、安眠のために遮光生地が良いです。ただし、暗すぎるのは困る時はある程度光が入る、遮光効果の低い2級や3級を選ぶと良いでしょう。朝日で自然に目覚めたい時は、非遮光をします。
寝室にいるのは、ほとんど夜だけという時はレースをつけずドレープのみで良い場合もあります。
寝室にいるのは、ほとんど夜だけという時はレースをつけずドレープのみで良い場合もあります。
寝室:落ち着く色
風水では使った運を補い、疲れを癒して明日の活力を生む重要な空間です。選び方に、決まりはなく家族がリラックスする色で良いですが、迷う時は以下の色を参考にしてください。
筋肉が1番リラックスする色はベージュになります。ベースカラーとして使い、ブラウンや色味をアクセントカラーに加えると良いです。カーテンも、無地ではなくベージュ地に柄が入っているものならうるさくなりません。
青や緑、ラベンダー色もです。紫は、青紫系にすると上品になります。明るめの落ち着いたトーンが落ち着きます。寝室や寝具の色で避けた方が良いのは黒やグレーです。陰の気が強く、運気を落とすと言われています。
筋肉が1番リラックスする色はベージュになります。ベースカラーとして使い、ブラウンや色味をアクセントカラーに加えると良いです。カーテンも、無地ではなくベージュ地に柄が入っているものならうるさくなりません。
青や緑、ラベンダー色もです。紫は、青紫系にすると上品になります。明るめの落ち着いたトーンが落ち着きます。寝室や寝具の色で避けた方が良いのは黒やグレーです。陰の気が強く、運気を落とすと言われています。
寝室:遮熱
夏や冬は、エアコンが欠かせません。でも、寝る時につけっぱなしでは乾燥するので避けたいところです。遮熱なら、屋外の熱や冷気を遮断するためエアコン効果が高まります。安眠のためには、部屋の暖かさや涼しさを保つことが大切です。
和室
障子は、光を和らげたり熱を防ぐ機能がありますがそれだけでは足りません。和室を寝室にしている場合の選び方は、遮光や断熱性のあるカーテンが良いでしょう。UVカットのレースをつけると、障子を開けた場合も畳の焼けを防いで長持ちさせます。
和室:畳コーナー
和室の中でも、床の間のある純和風から、洋風のリビングの一角にある畳コーナーまで種類があります。畳コーナーの場合、扉があっても開けたままで使うことが多いです。畳コーナーの選び方は、リビングの窓と一緒に視界に入るためお互いに調和するものを選びます。
選び方の順番としては、先にリビングのカーテンを選び、それになじむもので畳コーナーを考えるとまとまりやすいです。全く同じでなくても、柄の中の色がリンクしていたり、同じ色の濃淡でも調和します。
選び方の順番としては、先にリビングのカーテンを選び、それになじむもので畳コーナーを考えるとまとまりやすいです。全く同じでなくても、柄の中の色がリンクしていたり、同じ色の濃淡でも調和します。
和室:素材
素材の選び方として、メンテナンスを考えると、ポリエステルがです。ポリエステルのカーテンでも、ざっくりした素材やジャガード織なら和風のイメージに合います。柄も、シンプルを心掛けると和モダンになります。他には、和紙調のプリーツスクリーンやウッドブラインドも相性が良いでしょう。
和室:色
色の選び方は、和室と同じ系統の色であるグリーン・ベージュ・ブラウンなどアースカラーが相性抜群です。自然素材を活かすため、ナチュラル系のイメージにすると上手くいきます。ふすまの色や、畳の縁の色をリンクしてカーテンに使うとインテリアになじみやすいです。
リビングとひと続きの、畳コーナーの場合は、アクセントカラーとしてポイントで色を加えると、グッと引き締まるでしょう。えんじ色やオレンジは、鮮やかでも合います。少しトーンを落とした、ピンクや紫も優しい雰囲気です。
リビングとひと続きの、畳コーナーの場合は、アクセントカラーとしてポイントで色を加えると、グッと引き締まるでしょう。えんじ色やオレンジは、鮮やかでも合います。少しトーンを落とした、ピンクや紫も優しい雰囲気です。
ワンルーム
ワンルーム:広く見せる
狭いワンルームの選び方では、壁の延長線になるオフホワイト・生成り・ベージュ・パステル系を選ぶと広く見えます。ただ、寂しい印象になりがちなので家具やラグでアクセントカラーを入れて自分らしい空間にするのがです。
同じ目の錯覚として、横ラインのボーダーなら部屋を広く見せてくれるでしょう。部屋の中で、多くの色があると狭く見えるため家具とカーテンの色を合わせるとまとまりが出ます。
同じ目の錯覚として、横ラインのボーダーなら部屋を広く見せてくれるでしょう。部屋の中で、多くの色があると狭く見えるため家具とカーテンの色を合わせるとまとまりが出ます。
ワンルーム:プライバシー
ワンルームの選び方として、キッチンから食事、寝るところまで全て1つの空間であるためプライバシー対策が必要になります。遮光カーテン+ミラーレースの組合せがです。
一人暮らし
一人暮らしは、狭い空間の中で家具をあまり置けないためファブリックを統一するとまとまりのあるインテリアになります。選び方としては、カーテンとラグの色味を揃えましょう。柄を揃えたり、同じシリーズの色違いにすることでも統一感が出せます。
女性の選び方は、カーテンの透け感や漏れる光などプライバシーを考えなければいけません。花柄や女性らしい色のカーテンが、外から見えると女性の1人暮らしであることがわかるため覗かれたり犯罪にあう可能性があります。
遮光2級か3級なら、デザイン性も選べるためオフホワイト系の女性らしい柄にすることもできます。昼間も外から見えにくいミラーレースを合わせると良いでしょう。
女性の選び方は、カーテンの透け感や漏れる光などプライバシーを考えなければいけません。花柄や女性らしい色のカーテンが、外から見えると女性の1人暮らしであることがわかるため覗かれたり犯罪にあう可能性があります。
遮光2級か3級なら、デザイン性も選べるためオフホワイト系の女性らしい柄にすることもできます。昼間も外から見えにくいミラーレースを合わせると良いでしょう。
初回公開日:2017年11月07日
記載されている内容は2017年11月07日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。