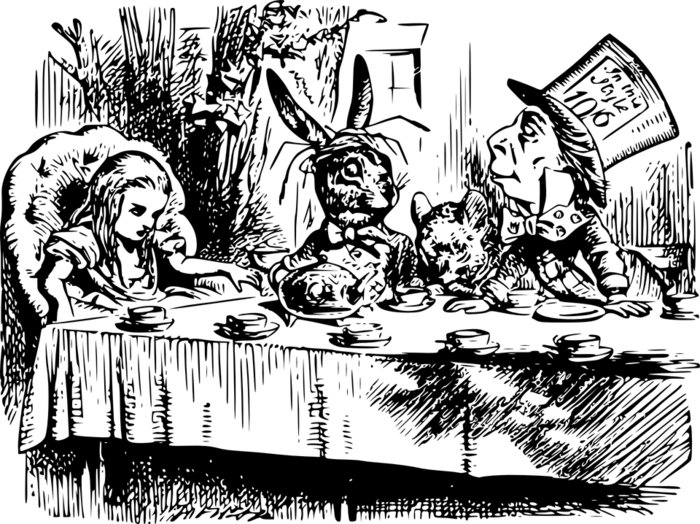おすすめの土鍋の目止めの方法・やり方|片栗粉/小麦粉/とぎ汁
更新日:2025年03月05日

土鍋本体の目止めが必要なら、蓋も目止めが必要なのでは、と考えますが、土鍋の蓋には釉薬(ゆうやく)と呼ばれるうわぐすりが塗られ、本焼きで表面にガラス層でほぼおおわれているため耐水性が高いことと、そもそも調理道具として蓋を利用することもありませんので、土鍋の蓋の目止めは必要ないと考えられます。
目止めのときに蓋はしないの?
土鍋の目止めをするときに蓋をすべきかどうかで悩むこともありますが、基本的に目止めのときに蓋はしないことをおすすめします。
理由は、蓋をすることで内部の温度が急激に上がってしまう可能性があるため、土鍋に負担をかけてしまうことと、おかゆなどを炊いたあと蓋をしていると冷めにくくなってしまうため、熱が取れにくくなり目止めの時間が余計にかかってしまうためです。
理由は、蓋をすることで内部の温度が急激に上がってしまう可能性があるため、土鍋に負担をかけてしまうことと、おかゆなどを炊いたあと蓋をしていると冷めにくくなってしまうため、熱が取れにくくなり目止めの時間が余計にかかってしまうためです。
土鍋の蓋が割れてしまったら
蓋だけを落として割ってしまったり、ぶつけて壊してしまったりすることがありますが、国産土鍋であれば、ほとんどの商品が蓋だけや本体だけといったようにパーツごとに購入することが可能です。
土鍋をパーツごとに購入できることは知られていないことが多く、あきらめて処分してしまう方もいますが、気に入って購入した土鍋なら、処分前に購入店に問い合わせてみてください。
土鍋をパーツごとに購入できることは知られていないことが多く、あきらめて処分してしまう方もいますが、気に入って購入した土鍋なら、処分前に購入店に問い合わせてみてください。
目止めをしなくても土鍋は使えるのか
うっかり土鍋の目止めを忘れてしまうことがありますが、そんなとき、土鍋を使っても大丈夫なのかが気になります。現在は目止めをしなくても使える土鍋も存在しますが、通常の土鍋の場合目止めを忘れてしまうと、使用後にぬるま湯などを入れてそのまま一晩おいたりすると土鍋の下に水が溜まったり、なべ底が濡れていたりすることがあります。
目止めをしていないと起こりやすいトラブル
土鍋は貫入と呼ばれる独特なヒビが入っていたり、底は植木鉢のような仕上がりになっていたりするため先ほどのような状態になってしまう他、目止めをしていないと料理の匂いや汚れがついてしまったり、弱いところから亀裂が入りひび割れを起こしたりすることがあります。
目止めは土鍋の使い始めに行わなければ意味がないともいわれることもありますが、使い始めてから改めて行うことも可能で、土鍋の素材によっては定期的に目止めを行うことでより長持ちし、愛用することができます。
目止めは土鍋の使い始めに行わなければ意味がないともいわれることもありますが、使い始めてから改めて行うことも可能で、土鍋の素材によっては定期的に目止めを行うことでより長持ちし、愛用することができます。
「目止めは使い始めに一度だけ行うもの」と思われがちなのですが、定期的に目止めを行うと、土鍋を強く保つことが出来ます。
https://www.zutto.co.jp/blog/category/maintenance/460
目止めの要らない土鍋について
土鍋とひと口にいっても、素材の違いにより目止めの必要のない土鍋もあります。
セラミック製の土鍋は細かい土が材料として使われているおかげで、他の土鍋でよくある水の染み込みや料理の匂い移りがほとんどなく、目止めの必要がありません。お手入れも楽でIH対応の土鍋も多いため、オール電化のキッチンでも使いやすい特徴があります。
こちらの土鍋は電子レンジでそのまま使用できるため、下ごしらえをレンジで行い、そのままガスコンロやIH調理も可能です。空焚きしても割れる心配がなく、金属製のブラシで洗うこともできます。土鍋を気軽に使いたい方におすすめな商品です。
セラミック製の土鍋は細かい土が材料として使われているおかげで、他の土鍋でよくある水の染み込みや料理の匂い移りがほとんどなく、目止めの必要がありません。お手入れも楽でIH対応の土鍋も多いため、オール電化のキッチンでも使いやすい特徴があります。
こちらの土鍋は電子レンジでそのまま使用できるため、下ごしらえをレンジで行い、そのままガスコンロやIH調理も可能です。空焚きしても割れる心配がなく、金属製のブラシで洗うこともできます。土鍋を気軽に使いたい方におすすめな商品です。
土鍋の目止めで焦げた場合
料理をしていてもうっかり焦げ付かせてしまうことがありますが、目止めで土鍋を焦げ付かせてしまうこともあります。焦げを見ると金属製のタワシやスプーンなどで削り落としたくなりますが、その方法で土鍋の焦げを落とそうとすると土鍋を傷めてしまう可能性があります。
そこで、土鍋の焦げを落とす方法を汚れの強さなどに応じてご紹介します。
そこで、土鍋の焦げを落とす方法を汚れの強さなどに応じてご紹介します。
焦げ付きが軽い場合
鍋の底がうっすらと茶色く焦げ付いた程度の軽い汚れなら、ぬるま湯、もしくは水を入れて軽く沸騰させたら、そのまま一晩おき、次の日に土鍋の水を捨てて布巾やキッチンペーパーなどで丁寧にこすってみてください。
強い焦げ付きの場合

強い焦げ付きなら重曹を使った方法がおすすめです。方法は
1.土鍋の焦げ付きに合わせて水を400~800ml入れます。
2.重曹を大さじ2~4杯くらい入れ軽く混ぜます。
3.弱火にかけ、重曹が溶けてぐつぐつと煮立ってきたら中火にして10分ほど煮立てます。
4.火を止め、触れるくらいまで冷めたらスポンジや指で焦げを擦り落とします。
重曹を溶かすときに威力を落とさないため水を使うことと、一度で落ちきらない場合は2~3回繰り返してください。
もし時間があるなら火を止めた後、一晩放置してからこすり落とす方法もあります。
1.土鍋の焦げ付きに合わせて水を400~800ml入れます。
2.重曹を大さじ2~4杯くらい入れ軽く混ぜます。
3.弱火にかけ、重曹が溶けてぐつぐつと煮立ってきたら中火にして10分ほど煮立てます。
4.火を止め、触れるくらいまで冷めたらスポンジや指で焦げを擦り落とします。
重曹を溶かすときに威力を落とさないため水を使うことと、一度で落ちきらない場合は2~3回繰り返してください。
もし時間があるなら火を止めた後、一晩放置してからこすり落とす方法もあります。
初回公開日:2018年02月23日
記載されている内容は2018年02月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。