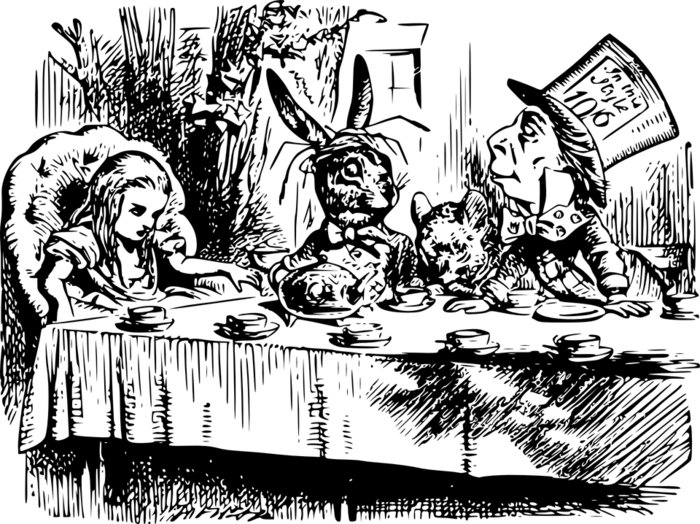干し柿にカビが生えた時の対処法・カビの見分け
更新日:2025年03月05日

青カビとも緑カビとも表現しますが、干し柿によく生えるカビが、緑色のカビと白カビになります。この青色がかった緑カビで、カビの度合いが酷くなく少量であれば取り除いたり、アルコールを吹き付けて、拭いたりすることでカビが取り除けるので、干し柿が食べる可能性が高いです。
しかし、少量なら食べられると言われている緑カビですが、いくらそう言われていてもカビですので心配な方などは、食べずに処分されてください。
しかし、少量なら食べられると言われている緑カビですが、いくらそう言われていてもカビですので心配な方などは、食べずに処分されてください。
黒カビ
干し柿にカビような黒い点ができることがあります。この黒い斑点ができる理由は2つあるので紹介します。
1つめの理由は、渋柿の渋み成分であるタンニンが関係しています。このタンニンが、干し柿を作る過程で柿の表面に出て塊になることで、黒い斑点のように見えています。
見た目はあまりよくないですが、柿から渋み成分のタンニンが外に出ているので、甘くて美味しい干し柿ができている証拠になります。干し柿に付いている白い粉のとこに黒い斑点ができている場合は、タンニンの可能性が高いです。
2つめの理由は、黒カビになります。干し柿を干している最中に、雨などに当たってしまうことでカビが生えてしまいます。カビが生え始めなら洗ったあとに、高濃度のアルコールを拭きかけて干すことで食べることができます。
同じ黒くなるでも斑点ではなく、全体的に黒くなることがあります。黒くなる理由は、干しすぎて乾燥しすぎたことのよります。
1つめの理由は、渋柿の渋み成分であるタンニンが関係しています。このタンニンが、干し柿を作る過程で柿の表面に出て塊になることで、黒い斑点のように見えています。
見た目はあまりよくないですが、柿から渋み成分のタンニンが外に出ているので、甘くて美味しい干し柿ができている証拠になります。干し柿に付いている白い粉のとこに黒い斑点ができている場合は、タンニンの可能性が高いです。
2つめの理由は、黒カビになります。干し柿を干している最中に、雨などに当たってしまうことでカビが生えてしまいます。カビが生え始めなら洗ったあとに、高濃度のアルコールを拭きかけて干すことで食べることができます。
同じ黒くなるでも斑点ではなく、全体的に黒くなることがあります。黒くなる理由は、干しすぎて乾燥しすぎたことのよります。
干し柿にできたカビの取り方
干し柿を作っている最中に、万が一カビが生えてしまったら、全てを処分しないといけないわけではありません。カビを綺麗に取り除ければ、干し柿作りを続行して、できあがった干し柿を食べることができます。では、カビを綺麗に取り除く方法はどんな方法があるのでしょうか。今回は「熱湯」「アルコール」「切り落とす」の3種類の方法を紹介します。
熱湯など

カビが発生した部分が少なければ、沸騰したお湯に、カビが発生してしまった干し柿を入れて、1分間ほど加熱します。それをまた天日干しして乾燥させてください。再度カビが発生しない場合は、カビを綺麗に取り除けているので、その干し柿を食べることができます。
再度干し柿を干すときは、柿同士を離したり、早く乾燥するように工夫してカビが生えないように気をつけてください。
再度干し柿を干すときは、柿同士を離したり、早く乾燥するように工夫してカビが生えないように気をつけてください。
アルコール

飲酒できるアルコール度数の高いお酒と綺麗な綿棒や布を準備し、それにアルコールを含ませて、干し柿にできたカビの部分を擦ります。そうすると、カビを取ることができます。
綺麗に擦ってカビを取った後は、使っているアルコールと同じ物をスプレーボトルに入れて、干し柿にアルコールを吹き付けたり、干し柿をアルコールに漬けます。そうすることで、アルコールの殺菌作用がカビを撃退してくれます。
アルコールで擦り落とした後は、柿をまた干していいですが、カビがまた発生するのであれば、その柿は処分してください。アルコールでの拭き取りに使われているアルコールは、焼酎やホワイトリカーなどが一般的ですが、アルコール度数の強いお酒が殺菌作用も強くなるので、できるだけアルコール度数の強いお酒ウォッカなどを使った方が、カビを撃退しやすいです。
その他に、干し柿を擦るのは綿棒や布以外では、使用してない新しい歯ブラシなど使いってもいいです。
綺麗に擦ってカビを取った後は、使っているアルコールと同じ物をスプレーボトルに入れて、干し柿にアルコールを吹き付けたり、干し柿をアルコールに漬けます。そうすることで、アルコールの殺菌作用がカビを撃退してくれます。
アルコールで擦り落とした後は、柿をまた干していいですが、カビがまた発生するのであれば、その柿は処分してください。アルコールでの拭き取りに使われているアルコールは、焼酎やホワイトリカーなどが一般的ですが、アルコール度数の強いお酒が殺菌作用も強くなるので、できるだけアルコール度数の強いお酒ウォッカなどを使った方が、カビを撃退しやすいです。
その他に、干し柿を擦るのは綿棒や布以外では、使用してない新しい歯ブラシなど使いってもいいです。
そぎ落とし

アルコールでの擦り落としでもカビが残ってしまったり、アルコールで拭き取るだけでは、内面や表面にまだカビが残っているかもと心配な方は、ナイフや包丁などでカビが付いてしまっている部分をそぎ落してください。そぎ落とした後の柿はアルコールを吹きかけるか、柿を丸ごとアルコールに漬けるかしてから再度干し直しをしてください。
そぎ落としをすることで、食べる面積は減ってしまいますが、カビが付いていた部分は全部切り落とすことができるので、他の方法よりも安心感があります。
そぎ落としをすることで、食べる面積は減ってしまいますが、カビが付いていた部分は全部切り落とすことができるので、他の方法よりも安心感があります。
カビを予防する方法
干し柿には、カビが天敵です。そのような干し柿を作る時にカビ予防方法はあるのでしょうか。もちろん、カビを発生させない予防方法があるので紹介します。
焼酎

干し柿を作る時のカビ予防に、焼酎などのアルコール度数の高いアルコールが使われます。干し柿を作る時に、スプレーボトルで干す柿にまんべんなく吹きかけておいたり、アルコールに漬けてから柿を干していきます。
その時の焼酎は、必ずアルコール度数35度以上を使ってください。同じ焼酎でも25度などの種類もあるので、しっかり確認してください。低いアルコール度数の焼酎では、カビ予防にはなりません。
また、忘れがちですが、干し柿を干して1週間後くらいに甘くするために柿を揉みますが、この揉む時も手を焼酎に浸して消毒してから揉まないと、まだ完成ではないので、そこからからカビが発生する可能性もあります。
その時の焼酎は、必ずアルコール度数35度以上を使ってください。同じ焼酎でも25度などの種類もあるので、しっかり確認してください。低いアルコール度数の焼酎では、カビ予防にはなりません。
また、忘れがちですが、干し柿を干して1週間後くらいに甘くするために柿を揉みますが、この揉む時も手を焼酎に浸して消毒してから揉まないと、まだ完成ではないので、そこからからカビが発生する可能性もあります。
アルコール
初回公開日:2017年12月01日
記載されている内容は2017年12月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。