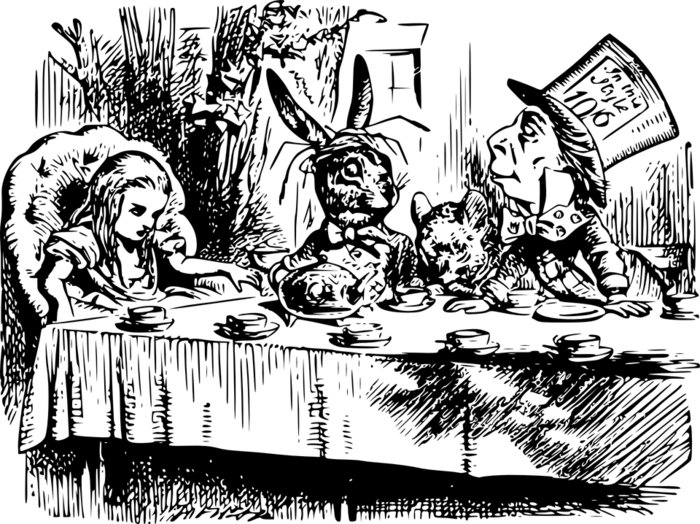ここが違う!「いくら」と「すじこ」の違い|レシピ6品も紹介
更新日:2025年03月05日

「いくら」と「すじこ」の値段
その時々で値段は変化しますが、一般的にいくらに比べてすじこは安価で販売されています。半額ほどで手に入ることも珍しくありません。いくらは、一粒一粒丁寧にほぐす手間が価格に表れていると考えられます。
いくらが食べたいけどなかなか手が出ないという場合は、新鮮なすじこを買って、自家製のいくらを作ってみるのもです。
いくらが食べたいけどなかなか手が出ないという場合は、新鮮なすじこを買って、自家製のいくらを作ってみるのもです。
「いくら」と「すじこ」の保存方法
いくらとすじこが塩漬けや醤油漬けで販売されているのは、保存性を高めるためです。生のものは保存がきかないため、旬の短い期間しか出回りません。
家庭で保存する場合は、いくらの場合は消毒した容器に入れ潰れないように空気を抜いて冷凍します。すじこは1本ずつラップにくるみフリーザーバックなどに入れて冷凍します。どちらも1ヶ月を目安に食べきりましょう。
家庭で保存する場合は、いくらの場合は消毒した容器に入れ潰れないように空気を抜いて冷凍します。すじこは1本ずつラップにくるみフリーザーバックなどに入れて冷凍します。どちらも1ヶ月を目安に食べきりましょう。
「いくら」と「すじこ」の食べ方
いくらは、寿司ネタや海鮮丼はもちろん、パスタやサラダのトッピングなどざまざまな食べ方が楽しめます。
それに比べて、すじこは塩蔵加工のものが多くしょっぱいため、あまりアレンジがききません。すじこの食べ方でなのは、シンプルにすじこだけを楽しむことです。ご飯に乗せてもいいですし、おにぎりの具やおつまみにもぴったりです。
それに比べて、すじこは塩蔵加工のものが多くしょっぱいため、あまりアレンジがききません。すじこの食べ方でなのは、シンプルにすじこだけを楽しむことです。ご飯に乗せてもいいですし、おにぎりの具やおつまみにもぴったりです。
すじこに挑戦したい方になのはこちら!
いくらは何度も食べたことがあるけれど、すじこは一度も食べた事が無いという方、案外いらっしゃるのではないでしょうか。すじこ未経験の方にしたいのが、サーモン専門店岩松の訳あり天然紅鮭筋子 (500g)です。
個体が細かったり切れていたりと見た目が少し悪い訳あり商品のため、お手頃価格で販売されています。しかし、味はとても美味しいと評判です。おにぎりやご飯のお供にぜひ食べてみてください。
個体が細かったり切れていたりと見た目が少し悪い訳あり商品のため、お手頃価格で販売されています。しかし、味はとても美味しいと評判です。おにぎりやご飯のお供にぜひ食べてみてください。
「いくら」と「すじこ」のレシピ5品

いくらとすじこを使った簡単レシピを厳選して5品ご紹介します。オーソドックスな丼物からパスタ、サラダなど盛りだくさんです。毎日色んなレシピで楽しめば、たくさん買ってもいただいても、あっという間に無くなってしまうでしょう。
1:親子でおいしい!簡単いくら丼

まずは、丼ぶりにしてイクラをたっぷり楽しみましょう。しかしただのイクラ丼ではありません。錦糸卵や大葉、海苔を散らせば色鮮やかで見た目も美しいイクラ丼の完成です。
錦糸卵さえ作れば、あとは材料を乗せるだけなので簡単です。大人はわさびをつけてぴりっと美味しくいただきましょう。
錦糸卵さえ作れば、あとは材料を乗せるだけなので簡単です。大人はわさびをつけてぴりっと美味しくいただきましょう。
材料 (4人分)
いくらのしょうゆ漬け適量
生卵2個
大葉1~2束(5~10枚)
きざみのり適量
ご飯丼1杯分
わさびチューブでもなんでもOK
醤油適量
砂糖適量
1
砂糖を入れて、錦糸卵を作ります。
※いくらにしっかり醤油味がついているので、卵に砂糖を入れて、少し甘めにしました。
2
大葉をくるくる巻いて千切りにし、ほぐします。
3
温かいご飯をどんぶりに盛り付けます。
4
錦糸卵をご飯の上に散らばせます。
5
錦糸卵の上に大葉を散らばせます。
※大葉が苦手なお子さんは、大葉なしでOKです♪
6
その上に、きざみのりを散らばせます。
7
一番上に、いくらの醤油漬けを乗せます。
8
好みの量のわさびを醤油でとき、最後に上からかけて、いただきます♪
※いくらにしっかり味がついているので、醬油は少なめに。
https://cookpad.com/recipe/4128750
2:簡単すし飯でカップ寿司

寿司によく使われるいくらですが、カップに入れるだけでパーティ料理に早変わりです。いくらやまぐろ、きゅうり、納豆、大葉などたくさんの具材を用意すれば、色んな種類のカップ寿司をつくることができます。
とても簡単なのに、見た目も華やかに仕上がります。ご家族や友人に喜んでもらえること間違いなしのレシピです。
とても簡単なのに、見た目も華やかに仕上がります。ご家族や友人に喜んでもらえること間違いなしのレシピです。
初回公開日:2018年12月20日
記載されている内容は2018年12月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。