洗濯槽の酸素系漂白剤・掃除方法|洗濯槽/臭い
更新日:2025年03月05日

洗濯槽の酸素系漂白剤ってどう使うの?

毎日のように活躍してくれる洗濯機ですが、洗濯槽の汚れが気になります。洗濯槽が汚れていると、洗濯物に臭いがついたり、カビが発生している場合はカビがついたりしてしまいます。洗濯槽は定期的に掃除をすることが大切です。洗濯槽の掃除に使う漂白剤は、酸素系漂白剤と塩素系漂白剤があります。酸素系漂白剤と塩素系漂白剤の違いや使い方などをご紹介しましょう。
塩素系漂白剤と酸素系漂白剤の違いは?
塩素系漂白剤は強い漂白力と殺菌力がありますが、生地を傷めやすく白い繊維にしか使うことができません。酸性の洗剤と混ざると塩素ガスが発生します。酸素系漂白剤は塩素系漂白剤に比べると漂白力は劣りますが、家庭で使うのには十分な漂白力です。白い繊維のほか色柄ものにも使うことができます。ここでは、塩素系漂白剤と酸素系漂白剤の違いを見てみましょう。
塩素系漂白剤とは?
塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムで漂白力が強いのですが、染料も落とす可能性があります。そのため、色柄ものには使えません。また、塩素系漂白剤は強いアルカリ性なので、綿や麻、ポリエステルなど使える繊維は限られます。
塩素系漂白剤は漂白力が強く、殺菌、除菌力が強いのが特徴です。漂白力が強いので繊維を傷めることがあります。また、塩素臭があるので使った後はすぐにすすいで、風通しのいい場所に干しましょう。
塩素系漂白剤は漂白力が強く、殺菌、除菌力が強いのが特徴です。漂白力が強いので繊維を傷めることがあります。また、塩素臭があるので使った後はすぐにすすいで、風通しのいい場所に干しましょう。
酸素系漂白剤とは?
酸素系漂白剤は、過酸化水素や過炭酸ナトリウムが主成分です。染料を落すことがないので、白物も色柄物にも使うことができます。酸素系漂白剤の形状には粉末と液体があります。酸素系漂白剤も除菌、殺菌力がありますが、漂白力は塩素系漂白剤より弱くなります。
・粉末タイプはアルカリ性で、過炭酸ナトリウムが主成分です。液体タイプよりも強力ですが、毛や絹などの動物系の繊維には使うことができません。
・液体タイプは酸性で、過炭酸水素が主成分です。毛や絹などの動物系繊維にも使うことができますが、注意書きに従って使いましょう。
粉末タイプも液体タイプも金属がついたものや、金属繊維のものには使うことができません。繊維の種類を確認して使うようにしましょう。
・粉末タイプはアルカリ性で、過炭酸ナトリウムが主成分です。液体タイプよりも強力ですが、毛や絹などの動物系の繊維には使うことができません。
・液体タイプは酸性で、過炭酸水素が主成分です。毛や絹などの動物系繊維にも使うことができますが、注意書きに従って使いましょう。
粉末タイプも液体タイプも金属がついたものや、金属繊維のものには使うことができません。繊維の種類を確認して使うようにしましょう。
酸素系漂白剤の効果
酸素系漂白剤の効果は洗浄、漂白、除菌、消臭があります。酸素系漂白剤は水と混ざることで、過酸化水素と炭酸ソーダに分かれます。過酸化水素は40℃以上のお湯で水素と酸素に分解されます。この酸素が汚れと結合して色素を一緒に分解します。
そのためシミを漂白したり、洗濯槽の汚れを浮かして綺麗にします。また酸素系漂白剤は、カビの原因になる細菌を洗浄してくれるので、除菌や消臭にも効果があります。洗濯槽は汚れが溜まる場所です。酸素系漂白剤を定期的に使えば除菌、消臭に効果が期待できます。
そのためシミを漂白したり、洗濯槽の汚れを浮かして綺麗にします。また酸素系漂白剤は、カビの原因になる細菌を洗浄してくれるので、除菌や消臭にも効果があります。洗濯槽は汚れが溜まる場所です。酸素系漂白剤を定期的に使えば除菌、消臭に効果が期待できます。
洗濯槽の掃除
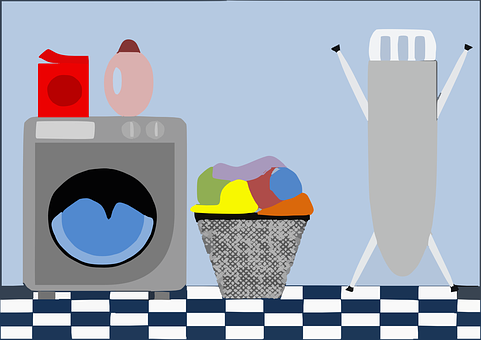
洗濯槽の掃除は、どのくらいの間隔ですれば効果があるでしょうか。1ヶ月に1回が理想だと言われていますが、平均すると2~3ヶ月に1回という方が多いと言われています。洗濯槽は汚れていても目につかない、裏側が汚れています。
洗濯槽の裏は、洗剤の溶け残りや衣服についていた食べかすなどにカビが生えてしまいます。洗濯槽の裏はカビの繁殖しやすい環境ですが、目に見えないので忘れがちな場所です。洗濯槽は定期的に掃除しましょう。
洗濯槽の裏は、洗剤の溶け残りや衣服についていた食べかすなどにカビが生えてしまいます。洗濯槽の裏はカビの繁殖しやすい環境ですが、目に見えないので忘れがちな場所です。洗濯槽は定期的に掃除しましょう。
洗濯槽の臭いの原因
洗濯槽が臭う原因の大半はカビ、雑菌、洗剤や柔軟剤、下水などです。洗濯槽が臭っていると、せっかく洗った洗濯ものに臭いが移ってしまいます。ここでは洗濯槽の臭い対策をご紹介します。
生臭い
洗濯槽が生臭い原因は雑菌です。洗濯槽で繁殖する雑菌はマイコバクテリウムという細菌が出す硫黄化合物といわれています。この細菌は湿気や温度、洗濯物についた汗や皮脂汚れなどを栄養として繁殖して臭ってしまいます。
洗濯槽に長い間洗濯物を置いておくと、細菌が繁殖してしまうので、洗濯物は終わったらすぐに出して干すようにしましょう。
洗濯槽に長い間洗濯物を置いておくと、細菌が繁殖してしまうので、洗濯物は終わったらすぐに出して干すようにしましょう。
カビ臭い
初回公開日:2018年03月11日
記載されている内容は2018年03月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

















