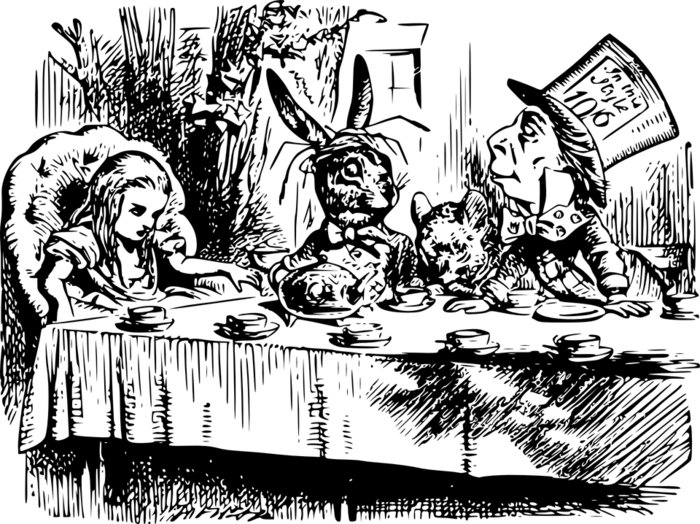日本酒の7種の酒器と特徴|酒器を使い分けて日本酒を楽しもう
更新日:2025年03月05日


「徳利」は日本酒が入っている酒器であり、猪口やぐい呑みに移すのが一般的です。首のところがスリムになっているのが特徴であり、空気に触れる部分が少ないため、日本酒の香りや温度を保つ効果もあります。
ガラス製のものは冷酒、陶器のものは熱燗でよく使用されます。ちなみに。徳利はお酒だけでなくそばつゆを入れるときにも使用されることがあります。
ガラス製のものは冷酒、陶器のものは熱燗でよく使用されます。ちなみに。徳利はお酒だけでなくそばつゆを入れるときにも使用されることがあります。
5:銚子

「銚子」は、徳利と同じ意味で使われることが多いですが、本来は急須のような形状のものをいいます。注ぎ口が1つの「片口」と2つの「両口」のものがありました。
江戸時代ごろに徳利などの小さな陶磁器が大量生産され、お酒を注ぐ酒器は銚子から徳利に変わりました。現在では、居酒屋で銚子1本と注文しても徳利が提供されます。
江戸時代ごろに徳利などの小さな陶磁器が大量生産され、お酒を注ぐ酒器は銚子から徳利に変わりました。現在では、居酒屋で銚子1本と注文しても徳利が提供されます。
6:片口

「片口」は、徳利よりも口径が大きく、お酒を飲むだけではなくおつまみなどを入れる小鉢としても使われることがある酒器です。片方に口がついているのが特徴であり、徳利や盃の代わりにもなります。
プラスチック製のものから漆器のものまでさまざまな種類の片口がありますが、日本酒の味わいや風味を楽しみたい人は、漆器の片口を使用することをします。
プラスチック製のものから漆器のものまでさまざまな種類の片口がありますが、日本酒の味わいや風味を楽しみたい人は、漆器の片口を使用することをします。
7:ちろり

「ちろり」は、真鍮や銅、銀などで作られた酒器です。そのため、熱伝導や保冷効果が高く、熱燗や冷酒でもおいしく飲むことができます。ちなみに、関西ではたんぽと呼ばれることもあります。
他の酒器と違って少し高級であり高価なものが多いですが、雰囲気のある酒器なので落ち着いて日本酒の味や風味を楽しむことができます。
他の酒器と違って少し高級であり高価なものが多いですが、雰囲気のある酒器なので落ち着いて日本酒の味や風味を楽しむことができます。
酒器を収納するときに商品はこちら!
酒器にこだわって集めると収納場所に困ってしまいます。高いところに収納した場合、落としたら割れてしまいます。重ねて収納した場合、取り出すときに落とす可能性が高くなります。そんなときに商品が「四季の盃」です。
この商品は、四季の盃が売りですが、自分の持っている酒器を収納することも可能です。1つ注意点として、酒器がどのくらいの大きさなのか把握してから購入してください。
この商品は、四季の盃が売りですが、自分の持っている酒器を収納することも可能です。1つ注意点として、酒器がどのくらいの大きさなのか把握してから購入してください。
酒器を使い分けて日本酒を五感で味わおう

前述したように、酒器は猪口やぐい呑みなどさまざまな種類のものが、さまざまな材質で作られています。材質が違うことで日本酒の色や香り、温度などが多少変わります。
今回は、なぜ酒器を使い分けることでたくさんの楽しみ方ができるのか紹介していきます。
今回は、なぜ酒器を使い分けることでたくさんの楽しみ方ができるのか紹介していきます。
1:日本酒を注ぐ心地よい音を聞く
酒器を使って飲むことで日本酒を注ぐ心地よい音を聞くことができます。特に、徳利や猪口を使うことで心地よい音を聞くことができ、飲む前から楽しむことができます。
このように、酒器にこだわることで注ぐときの心地よい音を楽しんだ後においしく飲むことができます。一般的なコップに日本酒を入れた時には心地よい音はほとんど聞こえてこないので、酒器の1つの楽しみ方と言えます。
このように、酒器にこだわることで注ぐときの心地よい音を楽しんだ後においしく飲むことができます。一般的なコップに日本酒を入れた時には心地よい音はほとんど聞こえてこないので、酒器の1つの楽しみ方と言えます。
初回公開日:2018年12月11日
記載されている内容は2018年12月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。