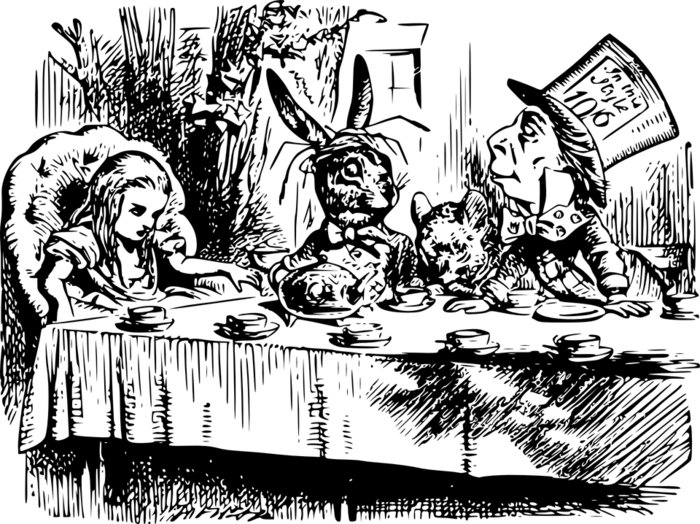日本酒の7種の酒器と特徴|酒器を使い分けて日本酒を楽しもう
更新日:2025年03月05日

酒器とは

「酒器」とは、お酒を飲むための器です。その種類はさまざまであり、銅や銀、漆器などといった材質で作られています。日本酒の味や風味を存分に引き出してくれるため、よりおいしく飲むことができます。
ネット通販でも購入することができ、リーズナブルなものから高級品までたくさんあります。ワインや焼酎のグラスをこだわるように、日本酒の酒器をこだわることでより楽しむことができます。
ネット通販でも購入することができ、リーズナブルなものから高級品までたくさんあります。ワインや焼酎のグラスをこだわるように、日本酒の酒器をこだわることでより楽しむことができます。
酒器を使い分けるメリット
日本酒の酒器はお猪口やぐい呑みなどたくさんありますが、それぞれ使い分けることでよりおいしく飲むことができます。その一番のメリットは、温度変化が少ないということです。
酒器によっては、一口飲む量だけを入れるものから底が深いものまであります。ビールのジョッキなどの大きさだと時間によってだんだんと常温になっていきますが、日本酒の酒器は、1つ1つが小さいため温度変化しにくいです。
酒器によっては、一口飲む量だけを入れるものから底が深いものまであります。ビールのジョッキなどの大きさだと時間によってだんだんと常温になっていきますが、日本酒の酒器は、1つ1つが小さいため温度変化しにくいです。
日本酒の酒器の種類と特徴

日本酒の酒器はさまざまなものがあります。熱燗で飲むのが最適なものから冷酒で飲むのが最適なものまで多種多様ですが、それぞれに特徴があり詳しく知ることで、より日本酒をおいしく飲むことができます。
今回は、日本酒の酒器として用いられる「盃・杯」「猪口」「ぐい呑み」「徳利」「銚子」「片口」「ちろり」の特徴などを中心に紹介していきます。
今回は、日本酒の酒器として用いられる「盃・杯」「猪口」「ぐい呑み」「徳利」「銚子」「片口」「ちろり」の特徴などを中心に紹介していきます。
1:盃・杯

「盃・杯」は、主に日本酒を飲むために使用される酒器です。漆器製やガラス製、金・銀・錫などの金属製や陶磁器製などさまざまな材質で作られています。
「盃」と「杯」は基本的に同じ意味を指しますが、「盃」は、酒を飲むために使用されるものであり、「杯」は、優勝したときに渡されるトロフィーや授与される賜杯などの意味合いが強いため、厳密には少し意味が異なります。
「盃」と「杯」は基本的に同じ意味を指しますが、「盃」は、酒を飲むために使用されるものであり、「杯」は、優勝したときに渡されるトロフィーや授与される賜杯などの意味合いが強いため、厳密には少し意味が異なります。
2:猪口

「猪口」は、ひとくちで飲みきれるサイズで、器に左右されることなくお酒を味わうことができるという特徴があります。
元々利き酒を行うために作られており、日本酒の透明度や光沢をチェックする酒器でした。現在では、居酒屋などで日本酒を頼むと温度に関係なくこの猪口が提供されることが多いです。
元々利き酒を行うために作られており、日本酒の透明度や光沢をチェックする酒器でした。現在では、居酒屋などで日本酒を頼むと温度に関係なくこの猪口が提供されることが多いです。
3:ぐい呑み

「ぐい呑み」は猪口よりも大きいサイズであり、ぐいぐい飲むことができることが名前の由来になっている酒器です。器の底が若干深めに作られているのが特徴であり、焼酎などでも使われることがあります。
加えて、透明なグラスのものが多く、日本酒や焼酎などの透明度や光沢を確かめながら味わうことができます。
加えて、透明なグラスのものが多く、日本酒や焼酎などの透明度や光沢を確かめながら味わうことができます。
4:徳利
初回公開日:2018年12月11日
記載されている内容は2018年12月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。