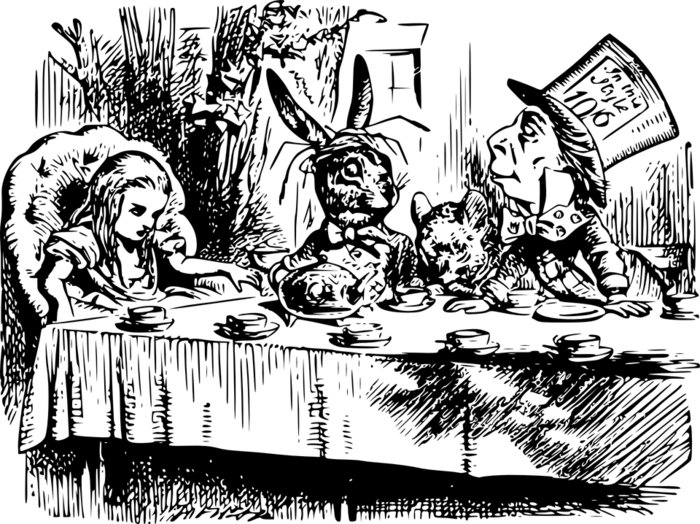スキムミルクの代用品は?スキムミルク活用レシピ5選
更新日:2025年03月05日

スキムミルクの代用に向いていないもの
これらの2つの乳製品を代用品にするのであれば、量を控え目にしましょう。レシピなどの分量にそって代用すると、濃度やとろみが付き過ぎて予想した状態にでき上がらないことがあるため注意してください。
スキムミルクと代用品との仕上がりの違い
牛乳の場合はレシピに書かれているよりも量を控えめにしましょう。水分も控えめにしてください。粉ミルクやクリーミングパウダーの場合は、こくが足りない場合があるので、多めに入れた方がいいでしょう。
スキムミルクの代用の仕方
スキムミルクの代用の仕方は、スキムミルクを基準にして脂肪分や水分の量が少ないか、多いかによって考えるようにしてください。
スキムミルクを使ったレシピ5選

1:冷凍野菜とスキムミルクで簡単ミルクスープ

お椀にスキムミルクを入れて混ぜるだけなので、思い立った時に気軽に作れて水っぽくならずに美味しくできます。野菜の旨みとスキムミルクの優しい味が良く合います。
材料はこんな感じ。お肉は鶏肉を使いました。もちろん豚肉でもおいしいです。薄切りの豚バラ肉なら手でちぎって入れちゃってOK。ベーコンやソーセージなんかを使ってもおいしく作れます。
玉ねぎは中サイズ4分の1個をくし切りにしています。玉ねぎを入れると甘みが出ておいしいので、具に追加を推奨。面倒だったら、冷凍ほうれん草と冷凍きのこミックスだけでもおいしいですよ。
冷凍ほうれん草は、以前このブログでも紹介した通り、下ゆでして使いやすいサイズにカットした状態で、ファスナー付き保存袋に入れて冷凍しておくと本当に便利です。こちらの 作りおき冷凍ほうれん草活用メニューまとめ も参考にしてください。
きのこは、しめじやまいたけ、しいたけ、えのきだけなんかを、食べやすい大きさにカットして混ぜ合わせ、生のままファスナー付き保存袋に平べったくなるよう入れて冷凍しておくだけです。一般的なサイズのしめじ1株、えのきだけ1株、小さめのしいたけ6枚くらいで、Mサイズの保存袋2つ分ですね。
作りおき冷凍野菜があれば、スープ作りも本当に簡単。お鍋にくし切りにした玉ねぎと、小どんぶりに8分目程度の量の水を入れて湧かし、沸騰したらお肉を入れます。味付けは、鶏ガラスープの素を使っています。お肉からいい出汁が出るので、顆粒タイプを小さじ1杯くらいかな。
玉ねぎとお肉が煮えたら、冷凍きのこミックスと冷凍ほうれん草を投入。凍ったまま入れちゃってOK。ほうれん草は下ゆでしてありますし、きのこは冷凍すると火の通りが速くなるようなので、投入したら1~2分も煮れば大丈夫です。
スキムミルクは、お鍋に直接入れちゃうとダマになりやすいので、小どんぶりのほうに大さじ1杯入れておき(私は山盛り1杯入れてるw)、鍋からお玉に1杯すくったスープで先に溶いておくといいです。そこに残りのスープをお鍋からざばーっと移してしまえば完成。
https://tekitou-gohan.site/archives/857
2:デパ地下風かぼちゃサラダ

粉チーズとスキムミルクを入れることにより、カボチャの甘さが引き立ち、まろやかになります。また、スキムミルクを入れることでカルシウムやタンパク質が加わり、栄養価も高くなるでしょう。
かぼちゃはシリコンスチーマーでやわらかくなるまでチン。
1/3個で2~3分だったか・・・。
そのままかぼちゃを軽くマッシュしたら、塩胡椒をして
スキムメルクを入れ、
さらに常備している酢漬け玉ねぎ(スライスした玉ねぎを酢に漬けているだけ)を入れ
ゆで玉子、パルメザンチーズ、マヨネーズを入れてまぜてできあがり。
マヨネーズ系のサラダのときにはたいてい酢を加えるのですが
これが入るだけでほんと美味しい。
さらにスキムミルクがいい感じにまろやかにしてくれて
しかも栄養がアップ。
これは定番にしたいくらい美味しくできました好き
<2人分>
かぼちゃ 2/3個
酢漬け玉ねぎ 1/4個くらい
塩胡椒 少々
スキムミルク 大さじ1
パルメザンチーズ 大さじ1
ゆで玉子 1個
マヨネーズ 大さじ2くらい
https://ameblo.jp/hanachandape/entry-11931671760.html
3:+スキムミルク カルシウム200mgプリン

黒糖とスキムミルクを使っていることから、ミネラル分とカルシウムがたっぷりで栄養分も豊富です。容器に入れて蒸す前にざるでプリン液をこすと、スキムミルクや卵のダマが残りません。滑らかで口当たりの良いプリンが作れます。
初回公開日:2018年12月10日
記載されている内容は2018年12月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。