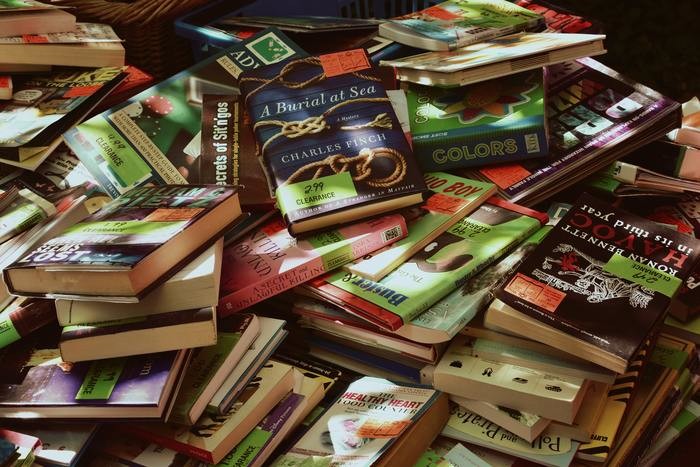畳のカビ対策|原因/予防・症状別カビの取り方・効果的な物
更新日:2025年03月05日

日本の誇る畳文化!その歴史とは?

みなさんのおうちには畳がありまか?ひと昔前までの日本の家屋には、畳は当然のようにどの家にもありました。家族みんなで畳の上でゴロンと横になった思い出がある人も多いのではないでしょうか?手入れを考えるとフローリングの方が手間がかからず掃除も簡単ではあるのですが、日本人はやっぱり畳の上が一番落ち着きます。
畳は、日本で生まれた伝統文化です。元々の畳は薄いゴザのような敷物であり、使わない時は折りたたんで片づけていたことから「たたむ」が変化して「畳(たたみ)」という名前になったと言われています。平安時代に入る頃から利便性や快適さ考えてクッション性の厚みを加えることになり、今の形になっていったと考えられます。
最近では日本人だけでなく、日本文化を好む外国人の方も畳を買い求めていくことがあるようです。日本が誇る畳の文化が外国人にも親しまれているのはとても誇らしいものです。
畳は、日本で生まれた伝統文化です。元々の畳は薄いゴザのような敷物であり、使わない時は折りたたんで片づけていたことから「たたむ」が変化して「畳(たたみ)」という名前になったと言われています。平安時代に入る頃から利便性や快適さ考えてクッション性の厚みを加えることになり、今の形になっていったと考えられます。
最近では日本人だけでなく、日本文化を好む外国人の方も畳を買い求めていくことがあるようです。日本が誇る畳の文化が外国人にも親しまれているのはとても誇らしいものです。
畳がもたらす健康への4つの効果とは?

日本独自の文化である畳ですが、フローリング等と比べて健康への効果に違いはあるのでしょうか?まず畳の材料ですが、畳はイグサという植物を編み込んで作られています。
イグサは国内の様々な地域で栽培されており、その品質によって畳の美しさや品質に違いが出てきます。近年ではリーズナブルな畳を求める消費者の声を反映し、価格の安い中国産などのイグサが使われることも多くなっています。
イグサでできた畳は何ともいえず気持ちの良い香りがするものですが、気になる畳の健康への効果はどうなのでしょうか?畳が体にもたらす4つの効果をご紹介します。
イグサは国内の様々な地域で栽培されており、その品質によって畳の美しさや品質に違いが出てきます。近年ではリーズナブルな畳を求める消費者の声を反映し、価格の安い中国産などのイグサが使われることも多くなっています。
イグサでできた畳は何ともいえず気持ちの良い香りがするものですが、気になる畳の健康への効果はどうなのでしょうか?畳が体にもたらす4つの効果をご紹介します。
マイナスイオンでストレスを解消できる
畳がもたらす健康への効果の1つ目は、マイナスイオンでストレスを解消できることです。
イグサを使った畳は驚くことにマイナスイオンを発生することが分かっています。マイナスイオンとは森や滝などからも発生されているとても体に良い物質で、マイナスイオンを体に取り入れると気持ちが落ち着きストレスも解消できると言われています。自宅に居ながらにして自然の恩恵が受けられる機会はなかなかありません。身近な畳でマイナスイオンを満喫しましょう。
また休日に自宅で読書をする時や、勉強に集中したい時などにも畳は効果を発揮します。畳を使った部屋では集中力が非常に高まると言われており、受験生や仕事をする人にもとてもです。
自宅にはぜひ畳の部屋を作り、家族みんなが落ち着く癒しの空間にしてみてはいかがでしょうか。
イグサを使った畳は驚くことにマイナスイオンを発生することが分かっています。マイナスイオンとは森や滝などからも発生されているとても体に良い物質で、マイナスイオンを体に取り入れると気持ちが落ち着きストレスも解消できると言われています。自宅に居ながらにして自然の恩恵が受けられる機会はなかなかありません。身近な畳でマイナスイオンを満喫しましょう。
また休日に自宅で読書をする時や、勉強に集中したい時などにも畳は効果を発揮します。畳を使った部屋では集中力が非常に高まると言われており、受験生や仕事をする人にもとてもです。
自宅にはぜひ畳の部屋を作り、家族みんなが落ち着く癒しの空間にしてみてはいかがでしょうか。
良い香りでリラックスできる

畳がもたらす健康への効果の2つめは、畳の良い香りでリラックスできることです。
畳のあの独特の素敵な香りは4つの主な成分が含まれています。畳の香りを構成する主な成分は、フォトンチッド、ジヒドロアクチニジオリド、α-シペロン、バニリンという4つがメインになります。
フォトンチッドとは森林などの木が放出する分泌成分です。フォトンチッドは思わず深呼吸したくなるほど良い香りであるだけでなく、消臭効果もあることが分かっています。
ジヒドロアクチニジオリドというのは少し聞きなれない言葉ですが、主に紅茶などの茶葉に含まれる香りです。単体ではほぼ香りを発しませんが、他の成分の香りを助ける役割を持っています。
α-シペロンは心を鎮める作用を持ちます。この成分を利用したアロマなども作られているほど高い効果があります。
バニリンというのはバニラの香りの成分のことです。甘いバニラの香りの成分が畳に含まれているというのは少し驚きですが、バニリンはストレスを軽減する作用があります。
畳の香りの成分は、これら4つの成分が混ざり合って生まれることであの安らぐ香りを作りだしているのです。
畳のあの独特の素敵な香りは4つの主な成分が含まれています。畳の香りを構成する主な成分は、フォトンチッド、ジヒドロアクチニジオリド、α-シペロン、バニリンという4つがメインになります。
フォトンチッドとは森林などの木が放出する分泌成分です。フォトンチッドは思わず深呼吸したくなるほど良い香りであるだけでなく、消臭効果もあることが分かっています。
ジヒドロアクチニジオリドというのは少し聞きなれない言葉ですが、主に紅茶などの茶葉に含まれる香りです。単体ではほぼ香りを発しませんが、他の成分の香りを助ける役割を持っています。
α-シペロンは心を鎮める作用を持ちます。この成分を利用したアロマなども作られているほど高い効果があります。
バニリンというのはバニラの香りの成分のことです。甘いバニラの香りの成分が畳に含まれているというのは少し驚きですが、バニリンはストレスを軽減する作用があります。
畳の香りの成分は、これら4つの成分が混ざり合って生まれることであの安らぐ香りを作りだしているのです。
抗菌作用がある
畳がもたらす健康への効果の3つめは、抗菌作用があることです。その昔、イグサは薬として調合されていたこともあるのをご存知ですか?イグサは自然素材でありながら非常に強力な抗菌作用があることが知られており、畳は日々の生活にとても役に立つことが分かってきました。
イグサが持つ抗菌作用は、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、O-157、レジオネラ菌、バチルス菌、水虫菌など多岐にわたる事が実証されています。畳を自宅に取り入れるだけで様々な菌から身を守ることができるとあって、赤ちゃんや小さな子供がいる部屋に畳を敷く人も増えています。イグサで出来た畳はフローリングと比較しても身体にとても優しいことがわかります。
イグサが持つ抗菌作用は、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、O-157、レジオネラ菌、バチルス菌、水虫菌など多岐にわたる事が実証されています。畳を自宅に取り入れるだけで様々な菌から身を守ることができるとあって、赤ちゃんや小さな子供がいる部屋に畳を敷く人も増えています。イグサで出来た畳はフローリングと比較しても身体にとても優しいことがわかります。
湿度を一定に保つ効果がある
畳がもたらす健康への効果の4つめは、湿度を一定に保つ効果があることです。
畳に使うイグサは顕微鏡で見ると無数の穴があいた構造になっています。イグサは湿度が高い時はこの穴に水分を閉じ込め湿気を取り、湿度が低い時は水分を放出し乾燥を防ぐとても便利な特性があります。イグサ1畳分でおよそ500ccも水分を吸収するともいわれており、寒い時も暑い時も部屋を常に快適に保つことが可能です。
高温多湿な日本の夏には、まるで呼吸をしているように自動で湿度を調整できる畳が非常によく合っており、まさに昔ながらの知恵を使った便利なアイテムといえるでしょう。
畳に使うイグサは顕微鏡で見ると無数の穴があいた構造になっています。イグサは湿度が高い時はこの穴に水分を閉じ込め湿気を取り、湿度が低い時は水分を放出し乾燥を防ぐとても便利な特性があります。イグサ1畳分でおよそ500ccも水分を吸収するともいわれており、寒い時も暑い時も部屋を常に快適に保つことが可能です。
高温多湿な日本の夏には、まるで呼吸をしているように自動で湿度を調整できる畳が非常によく合っており、まさに昔ながらの知恵を使った便利なアイテムといえるでしょう。
これはダメ!絶対にやってはいけない畳の掃除の仕方

では次に、畳を掃除する時の注意点を2つご紹介致します。みなさんは畳を掃除する時、どのように掃除をしていますか?
畳は汚れがそこまでひどくない時は、目に沿ってゆっくりと掃除機をかけて掃除をします。畳を敷いている部屋が庭に面している時は、ホウキでサッと掃いて砂などを落とすのも良いでしょう。
畳の汚れが目立つ時は、一度濡らし固く絞った綺麗な雑巾で優しく拭くようにします。畳はその特性から汚れを放置しておくとどんどん傷みが進みます。掃除はこまめにするのをします。
そして畳を掃除をする時には、絶対にやってはいけない注意点が2つあります。ついついやってしまいがちな2つの絶対NGな畳の掃除の仕方をご紹介します。
畳は汚れがそこまでひどくない時は、目に沿ってゆっくりと掃除機をかけて掃除をします。畳を敷いている部屋が庭に面している時は、ホウキでサッと掃いて砂などを落とすのも良いでしょう。
畳の汚れが目立つ時は、一度濡らし固く絞った綺麗な雑巾で優しく拭くようにします。畳はその特性から汚れを放置しておくとどんどん傷みが進みます。掃除はこまめにするのをします。
そして畳を掃除をする時には、絶対にやってはいけない注意点が2つあります。ついついやってしまいがちな2つの絶対NGな畳の掃除の仕方をご紹介します。
雑巾を絞らず水拭きする
畳を掃除する時に絶対にやってはいけないことの1つめは、雑巾を絞らず水拭きすることです。
汚れがひどい時はついつい畳を濡らして汚れを拭きたくなってしまいますが、畳を掃除する時は水拭きはNGです。湿気に強いと上記で説明した畳ですが、水拭きすると畳の水分の許容量を超えてしまい、カビが生える原因になってしまいます。
水分は畳の下へ下へと下りて行きます。表は綺麗でも裏を返せばカビだらけだった、というようなことにならないよう、雑巾はしっかりと固く絞って使うようにしましょう。
小さな子供がいる家庭など畳を汚しやすく、どうしても水拭きしたいという人は、天延のイグサを使った畳ではなく、ポリプロピレンやポリエステルなどで作られた商品を選んでみてはいかがでしょうか。
汚れがひどい時はついつい畳を濡らして汚れを拭きたくなってしまいますが、畳を掃除する時は水拭きはNGです。湿気に強いと上記で説明した畳ですが、水拭きすると畳の水分の許容量を超えてしまい、カビが生える原因になってしまいます。
水分は畳の下へ下へと下りて行きます。表は綺麗でも裏を返せばカビだらけだった、というようなことにならないよう、雑巾はしっかりと固く絞って使うようにしましょう。
小さな子供がいる家庭など畳を汚しやすく、どうしても水拭きしたいという人は、天延のイグサを使った畳ではなく、ポリプロピレンやポリエステルなどで作られた商品を選んでみてはいかがでしょうか。
初回公開日:2017年09月07日
記載されている内容は2017年09月07日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。