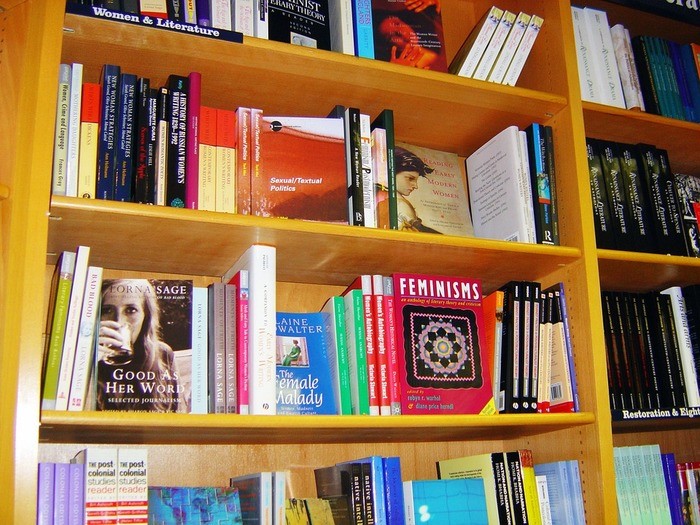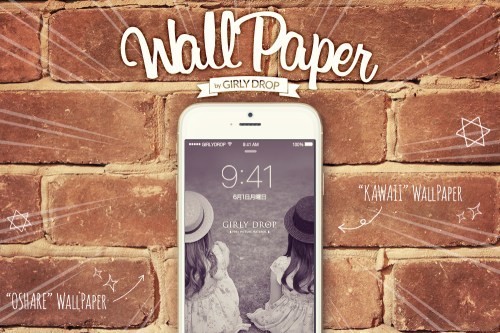ヨウムの平均寿命・寿命最長記録・飼育の仕方・オウムとの違い
更新日:2025年03月05日

そもそもオウムとヨウムは違うの?

一般的にオウムと呼ばれている鳥は「オウム目オウム科」に分類されています。しかし、ヨウムはセキセイインコやコザクラインコなどと同じように、「オウム目インコ科」に分類されています。小さくて愛らしいのが特徴的なセキセイインコと同じ動物ということに驚く人も少なくないでしょう。
外見でわかる違いは、オウム科の鳥は頭から立派な冠羽が生えていることです。ヨウム以外にも体の大きなインコはいますが、頭に冠羽がなければオウムではありません。逆に、セキセイインコなどと同じようにポピュラーな「オカメインコ」は名前にインコとついているものの、頭に冠羽が生えているためオウムの仲間となります。
外見でわかる違いは、オウム科の鳥は頭から立派な冠羽が生えていることです。ヨウム以外にも体の大きなインコはいますが、頭に冠羽がなければオウムではありません。逆に、セキセイインコなどと同じようにポピュラーな「オカメインコ」は名前にインコとついているものの、頭に冠羽が生えているためオウムの仲間となります。
寿命の違いはどれくらい?
オウムの寿命は種類によって多少の差はありますが、30~50年とされています。しかし、オウムの中でも体が小さなオカメインコは10~15年ほどです。寿命が50年ほどのヨウムと、一般的にオウムと呼ばれている大型の鳥との間に大きな差はないと言えるでしょう。
動物の寿命の長さを左右するのは体の大きさであることがほとんどです。キバタンやモモイロインコなどの大型のオウムと、ヨウムはどちらも体長が50cmほどと大きな差は見られません。
動物の寿命の長さを左右するのは体の大きさであることがほとんどです。キバタンやモモイロインコなどの大型のオウムと、ヨウムはどちらも体長が50cmほどと大きな差は見られません。
鳥類の中でのヨウムの寿命の長さ

ヨウムは平均寿命が50年とかなり長い鳥ですが、インコだけでなく他の鳥と比較してみてもその寿命は長いのでしょうか。代表的な鳥の寿命を以下の表に示します。毎日のように見かけている鳥から動物園で話題になっている鳥まで、さまざまな鳥と比べてみてもヨウムの寿命の長さがわかります。
| 種類 | 平均寿命 |
|---|---|
| コンドル | 60年 |
| フクロウ・ミミズク | 60年 |
| ダチョウ | 50~60年 |
| タンチョウ | 40年 |
| ワシ | 40年 |
| ハシビロコウ | 36年 |
| タカ | 30年 |
| ガチョウ | 25年 |
| カモメ | 20年 |
| ペンギン | 20年 |
| ツバメ | 12年 |
| カラス | 10年 |
| 鳩 | 10年 |
| キジ | 10年 |
| ニワトリ | 10年 |
| セキセイインコ | 7年 |
| カモ | 5~10年 |
| スズメ | 2~3年 |
| カワセミ | 2年 |
鳥類の中でも最も寿命が長いとされているのは、コンドル、フクロウ、ミミズク、ダチョウの仲間の60年です。そして、最短は川のヒスイと名高いカワセミの2年です。これを考慮してみても、ヨウムの寿命はかなり長いと言えるでしょう。
動物の寿命の長さは体の大きさに比例する場合がほとんどですが、ヨウムよりも大きな体の種類の鳥がヨウムよりも平均寿命が短いとされているのは不思議です。
動物の寿命の長さは体の大きさに比例する場合がほとんどですが、ヨウムよりも大きな体の種類の鳥がヨウムよりも平均寿命が短いとされているのは不思議です。
ペットというよりも「パートナー」

ヨウムはとても賢く愛情深い性格の動物です。人間でいうと2歳児の感情と5歳児レベルの頭脳を持っていることから、本当の子どものように可愛がる人も多いです。ペットとして飼われる動物の中では寿命が最も長いとされるヨウムは、ペットというよりも「人生のパートナー」という位置づけとなります。
ただのペットではなく本当の家族により近い存在を迎えたいと考えている人は、50年という長い寿命が終わるまでしっかり面倒を見られるのであればヨウムはインコです。どんどんレパートリーが増えるおしゃべりや仕草は見ていて飽きません。ヨウムと楽しい生活を送れるでしょう。
ただのペットではなく本当の家族により近い存在を迎えたいと考えている人は、50年という長い寿命が終わるまでしっかり面倒を見られるのであればヨウムはインコです。どんどんレパートリーが増えるおしゃべりや仕草は見ていて飽きません。ヨウムと楽しい生活を送れるでしょう。
初回公開日:2018年01月10日
記載されている内容は2018年01月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。